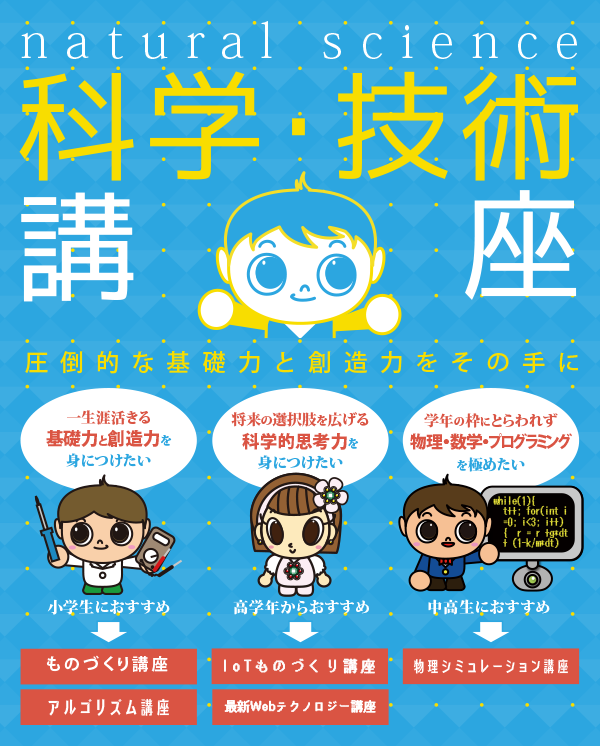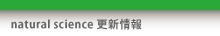第5回体験型自然科学の教室「海の教室」
青空実験場で「発見」!
自分でつかまえた生き物たち。顕微鏡でも見てみたい! お父さんやお母さんに助けてもらいながら、生き物たちの世界をのぞいていました。




(えらをめくってみて)
「このぱくぱくしてるの何?
ここにも口があるの?」

(疑似魚が水に浮いてうまく泳がないから)
貝を重りにして工夫してみたよ。
青空実験 1
魚の習性を利用した新漁法(?)の開発 (大野 科学者)
子どもたちがランダムに捕まえてきた、魚たち。種類が異なるにもかかわらず、魚たちはプールの中で群れをつくっていることに、前回の教室で、子どもたちが気づきました。それらの魚の行動から、その性質に一般性があるかどうかを調べたいと考えました。この「発見」を発展させた2つの実験系を、子どもたちと一緒に行いました。
<実験1> 魚は、偽りの魚と群れをつくるか?
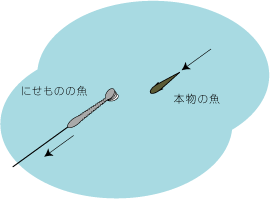
もし、自分たちと同じ形、もしくは同じでなくても形の特徴を捉えたなんらかの群れに他の魚も群れるという性質があれば、その群れを作ることで他の魚をひきつけることができるものと考えられます。従来の漁法、釣り方では擬似的な餌を用いることはあっても擬似的な仲間の群れを用いることはありませんでした。




一匹の魚が疑似魚についてくる効果が見られた。
その後擬似魚に食いつく様子はなかったことから
えさと間違ったわけではないようだ。
<実験2> 魚は、自らの像と群れをなすか?
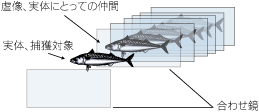
魚が群れを作るときに、もし同じ形の何かの近くに寄るという性質からそれができるのであれば最も"同じ形"である自分の虚像を見せてみてはどうでしょうか?しかも合わせ鏡をもちいることで無数の魚の虚像を作ることができます。魚は自分の虚像に寄り添うことで群れの中にいる気分を味わえるでしょう。群れのなかにいる気分を味わえるのは鏡の間のみですから、群れの中にいたい魚は鏡の間にとどまることが期待されます。
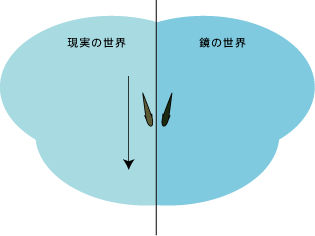

魚が鏡に沿ってある角度を保ちながら進む様子が見られた。
たける氏は「威嚇(いかく)している」と感じたことを表現していた。
群れを作ろうとしているのか、それともたける氏のおっしゃるように威嚇しているのかは不明だが鏡の方が普通の板に比べて魚道として働く可能性を示唆する結果となった。
青空実験 2
Dojou moves(ドジョウが出す力を定量化する実験) (林 科学者)
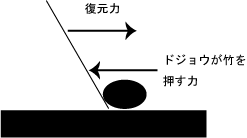
竹串を垂直にウレタンのシートにさします。 ウレタンは弾性体なので、復元力があり、 竹串がななめに傾けば、まっすぐなるように力が働きます。 ドジョウが竹串を押すと、斜めに傾くので、 傾いた角度を知ることで、ドジョウが出す力を知ることができると考えました。
結果としては、 ドジョウの活がわるかったので、竹串がうまくたおれなかったのが残念でした。ドジョウの定量化の実験は、自然の中では難しくて、 砂の上では、竹串を真っすぐ下にさせなかったりしました。 ドジョウが動く姿をはかったり、 力をはかったりする実験は実験室の中でやっていきます。

本日の助手のみなさん。
一緒に実験装置をつくっています。

砂をまぶしてからドジョウを放すなど、
子どもたちはそれぞれのこだわりを見せていました。
-目次-
| 蒲生干潟で「発見」! |
青空実験場で「発見」! |
「発見」がアートになったよ! |
協賛いただいた応援団の方々 |