第1回 natural science シンポジウム(2008.07.13)
サイエンスライブ報告(1/3)【林 叔克】
サイエンスライブ 概要
一般向けにサイエンスカフェとして、専門家による科学技術の成果の発表は頻繁に行われているが、このような大きなプロジェクトの成果発表では、研究成果の華やかさはあるものの「科学のプロセス」そのものを実感することは難しい。それに対しnatural scienceのサイエンスライブは「科学のプロセス」を明らかにしながら、研究の成果を発表するものである。研究の内容も日常的な感覚の中からうまれる素朴な疑問を出発点とし、異なる分野の科学者が、週末に集まって研究したものである。研究成果の発表は、研究の進行の臨場感をできるだけ伝えるライブ形式でおこなう。研究をはじめる際の素朴な疑問から観客と共有し、研究の背景として必要になる知識は、観客をまきこんで実験を行う。一見、あたりまえに思えることに「そもそも、なんでだろう?」と立ちどまって考える科学者の姿勢、研究が進むにしたがって論理的な筋道ができてくる様子を伝えることを目的とする。この「科学のプロセス」を通して「そもそも、科学ってなんだろう?」という問いの答えに実感をもってもらえれば幸いである。
(※サイエンスライブの様子はこちらをご覧ください。)
人の五感の研究
人は五感によって外界を知覚している。本研究では五感の中でも聴覚に注目し、実験を行った。人はどのように音源の場所を知覚しているのだろうか、音源の場所を判断する原理を探った。音は空気の振動であり、原理的に「振幅」と「周波数」によって記述される。振幅が大きいほど、大きな音として認識され、周波数は音の高低として認識される。人は音の大小と高低を聞き分けるだけでなく、音源への方向性と距離を知覚できる。例えば暗闇の中での視覚からの情報がない場合でも、ある程度、音源の位置を認識することができる。
この外界における音源の位置情報は、人の認識の中で音像と呼ばれる。ひとつの音源にたいし、人は左右の耳で聴きながら、ひとつの音像として認識する。これは音像の形成には両耳に到達する音の振幅差と音の到達時間が異なるという原理を利用していると考えられる。そこで本研究では、音の振幅差と到達時間の差による音像の方向を測定する実験をおこなった。実験手法としては、コンピュータプログラミングによって両耳に対する音の振幅の差、到達時間差をつくりイヤホンに出力し、被験者の音源の方向の認識を測定した。実験結果から、ひとつの音源から生じた音をふたつの耳で捉えることによって、両耳間に生じたわづかな音量さと音の到達時間差を知覚し、方向の認識としていることが明らかになった。つまり両耳で受聴した二つの音は、頭の中で統合され、方向感覚をともなって、ひとつの音像として認識されている。人の両耳の感覚は十数cmであるが、この感覚と頭部による音の遮蔽・回折によって、音量差と音の到達時間差がうまれるのである。
週末研究でえられた実験手法と知見をもとに、サイエンスライブでは「そもそも、人は音源をどうやって認識しているのか」、「なぜ、耳はふたつあるのか」という問いかけから始まる探求を観客と共有した。
サイエンスライブの構成
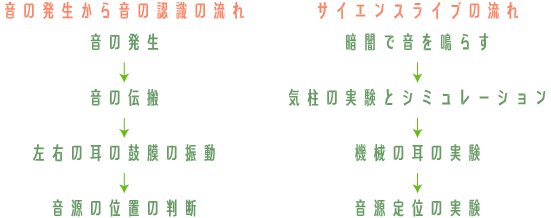
研究のプロセスと研究内容を理解するのに必要な知識を自然な流れの中で観客と共有するために、音が生じるところから、音が空気中を伝わって、人にって認識されるまでの流れをサイエンスライブの流れとした。各ステップにおいて、空気を伝搬する様子、空気の振動によって、人工の膜が振動する様子など、音が伝搬する過程を実験によって可視化した。音の性質が明らかになった時点で、観客を被験者として巻きこみ「人はどのように音源を認識しているのか?」という疑問の解明に迫った。
当日のライブの進行は、MCが「そもそも、科学とはなにか?」という視点で司会をつとめ、かがくしゃ二人が対話形式で実験と考察を展開し、かがくしゃのたまごが、観客を巻き込んだ実験を行った。以下にそれぞれの実験の説明とサイエンスライブの流れを書く。
音を「みる」実験
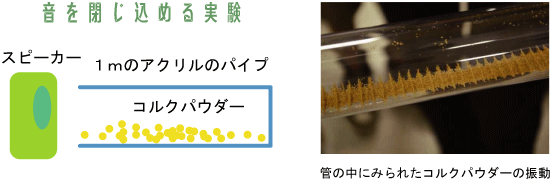
普段、音を聞くものだが、まず、音をみてみよう! 空気の振動を定量的に可視化するために、アクリル管を用いて、管の中の空気の振動をみる実験を行った。管の中に送り込む音の周波数を上げていき、ある周波数のところで、コルクのパウダーが振動しはじめた。この実験により空気の振動が可視化できた。共鳴した周波数は、80Hzと240Hzであり、音速が320m/sであることにより、1mの管の中で、1/4波長、3/4波長の波ができたと考えられる。写真のように管の中にみられた数cm間隔での振動は、空気の対流による2次的な振動である。
コンピュータシミュレーションによる検証実験
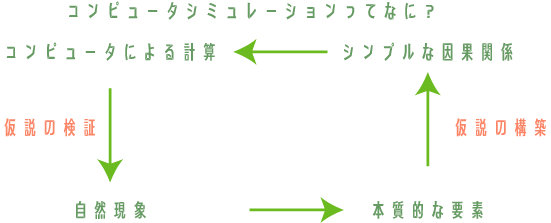
得られた実験結果に対して、どのように考察していくのか、科学者が仮説をたてるところから始めた。コルクのパウダーが周期的なパターンがつくっている様子をみて「音は周期的なものが、移動しているのではないか」という仮説をたてた。この仮説を検証するために「コンピュータシミュレーション」という手法を用いたが、この手法は、自然現象から本質的な要素を抜き出して、シンプルな因果関係を構築し、コンピュータに実験するという手法である。実際に仮説が正しいかどうかは、シミュレーションによって得られた結果が、実際の実験結果とどれぐらい整合性があるのかで、判断される。
今回の音の実験では、アクリル管に入ってくる波と管の端で反射して、出ていく波を重ね合わせたときに、定在波ができることをシミュレーションで示した。空気の振動が大きいところ、小さいところがあることが、コルクパウダーがつくる縞模様に対応しているのでは?ということで、「音は周期的な波が、移動しているのである」とまとめた。
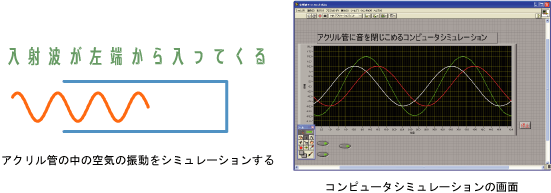
波の式を音を表す
それでは、波をもっともシンプルに表すには、どうしたらいいのだろうか?y=Asinωtという数式を使って、Aが波の振幅を表すこと、ωが波の振動数を表すことを話した。では、この式を使って、音を表してみよう!ということで、振幅の大きさが音量に対応し、振動数が音の高低に対応していることを実験した。
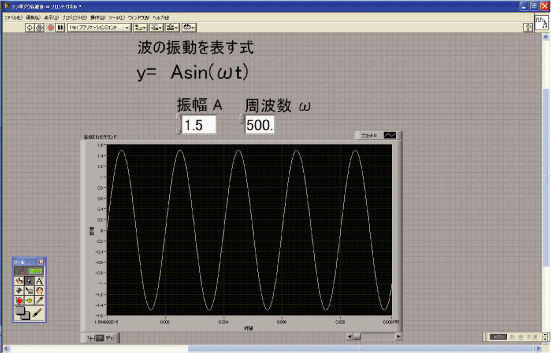
音の性質に基づいた「機械の耳」の実験
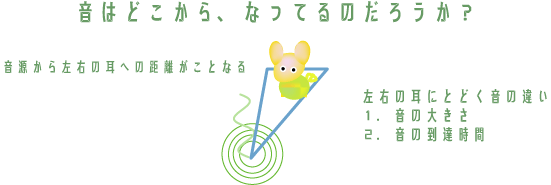
機械の耳で音を聞いてみよう!とマイクを二つ用意して、スピーカーからの音源をひろった。マイクの位置、スピーカの位置によって、左右のマイクがサンプルする音の振幅が変化する様子や、左右の耳に届く音の到達時間が変化する様子が観察された。この実験で明らかになったことは、
音源から左右の耳までの距離がことなる場合、
1.左右の耳に届く音の大きさが異なる
2.左右の耳に届く音の到達時間が異なる
という2点である。このことから音源までの距離と方向を原理的に特定する方法を提示した。人が左右の耳に届く音の大きさと到達時間の差を認識できるのであれば、
1.左右の耳に届く音の大きさの比が等しい位置を結んだ曲線
2.左右の耳に届く音の到達時間の比が等しい位置を結んだ曲線
の二つの曲線の交点に音源が存在することを認識できるはずである。この視点からみればマイクでサンプルした音は、人の鼓膜の振動を捉えていると考えることができる。
この原理の問題点として、二つの曲線の交点は人間の頭に対して、前後に2点存在するので、前から音が聞こえてくるか、後ろから音が聞こえてくるかの差は生まれてこないことがあるが、人の耳の場合は、前後の非対称性があるので、音源の位置を一点に特定できると考えられる。
人はどうやって、音源の位置を認識しているのか?
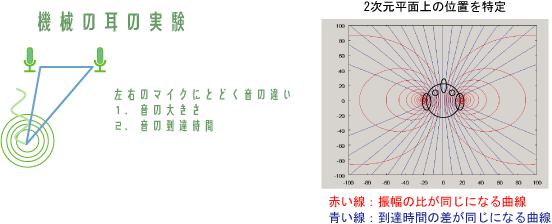
「機械の耳」の実験で明らかになった原理をもとに「人はどうやって、音源の位置を認識しているのか?」という実験に入った。ひとつの音源からの左右の耳への距離が違うので、左右の耳が受聴する音には以下の二つの差が生まれる。
1.左右の耳における音の大きさの差
2.左右の耳における音の到達時間の差
サイエンスライブでは観客が参加しやすい形にするため、スピーカを用いた受聴実験を行った。
1と2の実験ともに、左右のスピーカからの音量・到達時間差と主観的な音像の位置との対応を認識してもらうために、左右のスピーカからの音量の差・到達時間差を知らせた上で、どちからから音が聞こえてくるように感じるかを認識してもらった。今回の実験では、音像の方向を「左」「真中」「右」の3通りの中から選択する。このようにまず、音の方向感覚の判定基準をつくることが、主観的な音像の方向感覚による認識に重要である。
1の実験においては、左右のスピーカからの音量に差をつくり、
1.左のスピーカからの音量が大きい場合
2.右のスピーカからの音量が大きい場合
3.左右のスピーカからの音量が等しい場合
の3つのパターンをランダムに出力して、被験者の音像方向の選択とスピーカの出力パターンとの比較による識別率を測定した。
2の実験では、左右の耳に届く到達時間の差をスピーカから出す音のタイミングで実現する。この実験でも以下の3パターンの音をランダムに出力した。
1.左のスピーカからの音の到達時間が短い場合
2.右のスピーカからの音の到達時間が長い場合
3.左右のスピーカから音の到達時間が等しい場合
被験者の音像方向の選択とスピーカの出力パターンとの比較による識別率を測定した。
さらに人が両耳で受聴するさいに、どれだけの音量の差を知覚し、音源の方向を判断しているのかを測定するために、左右のスピーカから音量差を減少させ、被験者に受聴してもらった。音の到達時間差による音像方向の認識に関しても、到達時間の差を減少させ、人がどれほどの到達時間差魔で知覚し、音像方向の認識ができるかという実験を行った。
人はどうやって、音源の位置を認識しているのか?
サイエンスライブの中で、観客の方々に被験者になってもらい音源の認識の実験を行った。実験条件としては、雑音、壁による音の反射など条件が揃わない面があったが、観客全員が実験に参加し、スピーカを音源とした音像の認識をすることができた。
左右のスピーカからの音量の差を減少させていき、被験者が音像を方向感覚をともなって認識できる限界を調べた結果、左右のスピーカからの音の振幅の差が1.3倍になるまで音像を方向感覚をともなって認識できることがわかった。音の耳に到達する際のエネルギーは、体積と表面積の関係から、距離に反比例して減衰する。1.3倍の振幅の差は1メートル先に音源があったときに、30cmの到達距離の差によってうまれる振幅の差である。両耳間の距離は十数cmなので、音量差を知覚することで、数メートルの範囲にある音源の方向を判断できることを示唆している。
次に左右の耳に届く到達時間の差を利用した音源の方向の認識の実験を行った。0.0003秒の時間差からはじめて、0.0001秒の時間差までをスピーカから出力する実験を行った。0.0001秒の時間差まで、識別できる被験者が小数だが存在した。音速が320m/sであることを考えると、0.0001秒の時間差は距離にして約3cmである。このことを利用すれば、音源に対し少し首をかしげるだけで、左右の耳への到達時間の差がうまれ、音源の方向が認識できることがわかる。
日常的に聞いている音は、1.音の大きさの差と2.音の到達時間の差の二つの要素の両方がある状態で聞こえてくるが、本実験により人はそれぞれの要素を個別に認識できることがわかった。
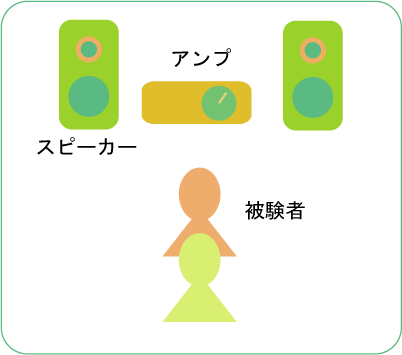
サイエンスライブにおける実験系
スピーカからの音を受聴し、主観的な音像の方向を答えてもらった。
人はどうやって、音源の位置を認識しているのか? イヤホンによる実験
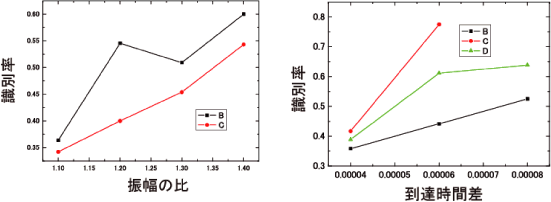
スピーカによる受聴の場合には、音源から両耳まである程度の距離があるため、左右それぞれの音を両耳で受聴することになる。そこで左で発生した音は左の耳で、右で発生した音は右の耳で受聴するという実験条件で行った。実験手法としてはイヤホンを使用すればよい。イヤホンによる受聴の場合は左右でまったく別の音を聞くため、自然の状態ではありえない実験条件であるが、この場合でも音像を方向感覚をもって認識できるかは興味ある問題である。
基本的な実験の方法はスピーカでの実験と同様で、左右のイヤホンからランダムに3種類のパターンの音を出力し、被験者に主観的な音像の方向を答えてもらった。実際の出力との整合性から、音源の方向の識別率を測定した。音の周波数は、200Hz とした。音の振幅の差による識別率の変化が左上図である。被験者に依存するところはあるが、おおよそ、1.2倍の振幅の左を識別し、音像の方向を認識しているようである。音の到達時間の差による識別率の変化が右上図である。0.0006秒の到達時間の差を知覚し、音像の方向を認識しているようである。つまり、左右の耳でまったく異なる音を受聴した場合でも
1.左右の耳における音の大きさの差
2.左右の耳における音の到達時間の差
を知覚し、音像の方向を認識していることが明らかになった。
人はどうやって、音源の位置を認識しているのか? まとめ
「人はどうやって、音源を認識しているのか?」という素朴な問いかけから始まり、人は耳がふたつあることを利用し、音の方向を認識していることを明らかにした。研究のプロセスと研究内容を理解するのに必要な知識を自然な流れの中で観客と共有するために、音が生じるところから、音が空気中を伝わって、人にって認識されるまでの流れをサイエンスライブの流れとした。各ステップにおいて、空気を伝搬する様子、空気の振動によって、人工の膜が振動する様子など、音が伝搬する過程を実験によって可視化した。このように音の性質を客観的に明らかにすることと、音源の位置を音像という認識の世界の中で、主観的に認識することを観客を巻きこんで実験した。素朴な疑問から始まる科学のプロセスが実感できるサイエンスライブになったと思う。

































