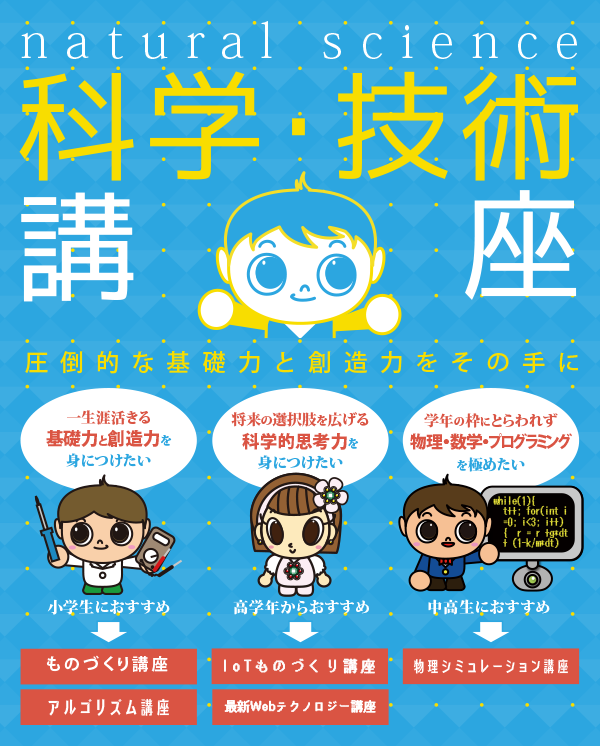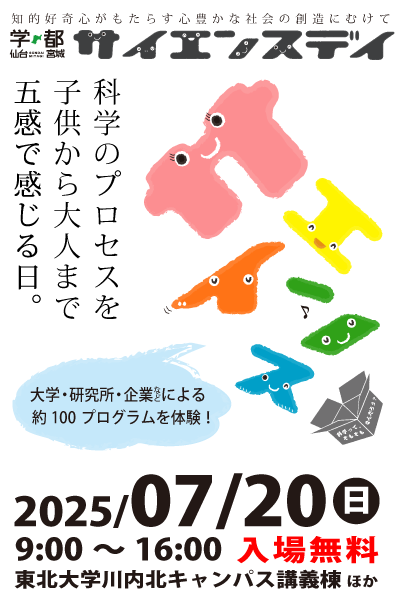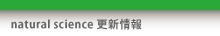蒲生干潟での観察(第8回「海の教室」)
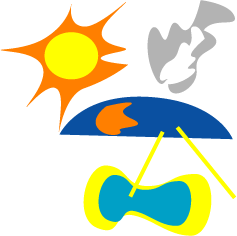
ステップ1
子どもようのプールの中に生き物の世界を切り出します。
海ってなんでしょう? 波、砂花、魚、かに、いろんな生き物がいるところ。
蒲生干潟という大きな自然の中から、海をきりだしてきます。
ステップ2
貝、あさり、さかな、くらげ、子どもたちが捕まえてきた生き物を観察します。
1.カニが潜んでいる石かたら、いろんな方向にすこし離してやると、もとの場所に戻っていくことから、カニはプールに入れられると、まず自分のすみかを決めているようだった
2.カニが弱った魚を食べるなどの食物連鎖がつくられていた
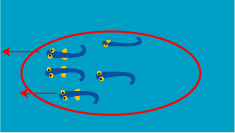
ステップ3 大野かがくしゃの魚の実験
タイドプールからさらに、実験系を切り出します。
さかなの群れの形成の実験です。
1.さかなは、ある範囲に集まっていた
2.さかなは、体の方向をそろえる
3.さかな同士の距離はほぼ一定間隔だった
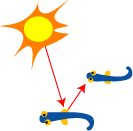
ステップ4 さかなの群れの考察
群れをつくるさいの、さかな同士のコミュニケーション方法として、
「光、水の圧力、化学物質のひろがり」が考えらるが、
さかなの動きの速さをみていると、光を情報伝達に使っていると思われる。
さかなの側面は、鏡のように光沢がり、この鏡を使って、光を反射させることで、
お互いの角度と位置を調節しているように思える。
また、もっとも近い所にいる魚からの光の反射のみを情報としていると
仮説を立てる。
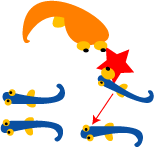
ステップ4 さかなの群れの考察2
さかなの群れを棒で攪乱してみると、さかなの群れは群れをつくったまま
逃げる行動が見られた。ある場所における変化がどのように群れ全体に伝わるか?
以下、仮説
1.まず、一匹が視覚的、あるいは水の圧力を感じて、物体の接近を感知する
2.その個体が角度を急にかえるので、隣のさかなへの光の反射の角度が変わる
3.となりの魚は、目に入ってくる光の角度が急にかわるので、その角度に対応して、
体を急回転させる
4.この回転がさらにとなりのさかなに伝わって、群れ全体として、物体からにげる
しかし、さかなの群れは、攪乱がなくても、全体として太陽光に対する角度を変えながら、
移動してるので、さかなが感知しているのは、角度そのものではなくて、角度がある時間の間に変化した量だと考えられる。
また、さかなの群れがふたつに分かれて、逃げる場合もあるので、この場合は、
分かれていくラインでは、角度を揃える方向と逆の方向に体を回転させるので、他のメカニズムが必要だと思われる。
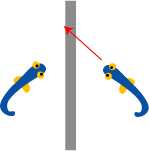
ステップ4 さかなの群れの考察3 大野かがくしゃとの議論
鏡に対して、斜め(45度ぐらい)で進む魚を発見。
鏡を意識しているのは確かなようだが、鏡の中のさかなとのコミュニケーションはうまくいかないようで、鏡にぶつかることを繰り返していた。